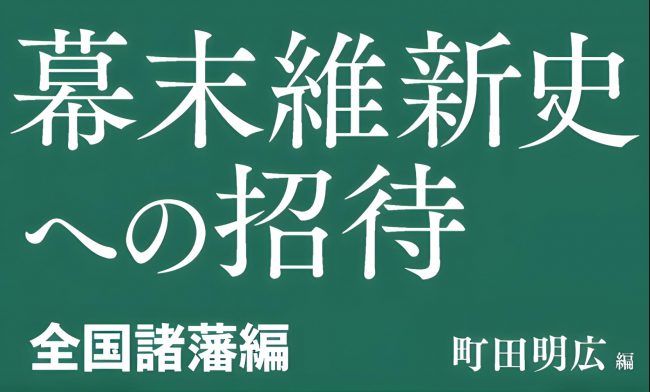日本研究所の町田明広教授が編集した新刊『幕末維新史への招待 全国諸藩編』が2025年9月25日に山川出版社より刊行されました。
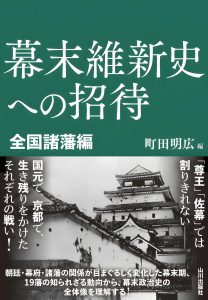 町田明広教授は日本近現代史(明治維新史)を専門とし、本学の附属研究機関「日本研究所」の所長も務めています。本書は「幕末維新史への招待」シリーズの第3弾として位置づけられるもので、朝廷・幕府・諸藩の関係が刻一刻と変化した幕末維新期を、全国19藩の動向から描き出したものです。中央政府主導の出来事に注目しがちなこれまでの歴史像に対し、各藩が直面した葛藤や意思決定に光を当てることで、政治史の全体像を立体的に再構築します。こうした地域の視点を重視したアプローチは、今年5月に刊行された『幕末維新史への招待 国際関係編』とも呼応するものであり、国内外の視座を往還しながら明治維新を多角的に読み直す試みです。
町田明広教授は日本近現代史(明治維新史)を専門とし、本学の附属研究機関「日本研究所」の所長も務めています。本書は「幕末維新史への招待」シリーズの第3弾として位置づけられるもので、朝廷・幕府・諸藩の関係が刻一刻と変化した幕末維新期を、全国19藩の動向から描き出したものです。中央政府主導の出来事に注目しがちなこれまでの歴史像に対し、各藩が直面した葛藤や意思決定に光を当てることで、政治史の全体像を立体的に再構築します。こうした地域の視点を重視したアプローチは、今年5月に刊行された『幕末維新史への招待 国際関係編』とも呼応するものであり、国内外の視座を往還しながら明治維新を多角的に読み直す試みです。
プレスリリース(続)はこちら
山川出版社のHPはこちら
ご購入はこちら(Amazon.co.jp)
***
目次:
はじめに――個別研究の時代から全体を結ぶ「論」の構築へ 町田明広
序章【幕末前史】朝廷・幕府と諸藩の関係史 町田明広
第1部 親藩・譜代大名編
- 1 章【水戸藩】「尊王攘夷」の虚と実、その光と影 由波俊幸
- 2 章【尾張藩】「親藩」としての行動を体現した新政府への参加 藤田英昭
- 3 章【会津藩】朝幕関係の「濾過装置」がもった政治的影響力の実態 白石 烈
- 4 章【福井藩】近代日本のミドルクラスを醸成した教育改革 熊澤恵里子
- 5 章【長岡藩】公武合体を見据えた「中立」という選択 小川和也
- 6 章【彦根藩】井伊直弼の名誉回復を願って結束した中下士層 野田浩子
- 7 章【加賀藩】徳川家との親疎関係が招いた、一貫した「正義」への誤解 宮下和幸
第2部 西南雄藩編
- 8 章【芸州藩】薩長と並ぶ倒幕の中心は、なぜ新政府で影を潜めたのか 三宅紹宣
- 9 章【長州藩】王政復古史観により創られた「過激派」イメージの検証 道迫真吾
- 10 章【土佐藩】真の主役・山内容堂に光をあててみえてくるもの 家近良樹
- 11 章【対馬藩】日朝通交と幕末政治史はどうリンクしたのか 松本智也
- 12 章【福岡藩】藩政を左右した藩主と家臣の複雑な関係性 高山英朗
- 13 章【佐賀藩】新政府中枢の一角は、ほんとうに倒幕勢力だったのか 大庭裕介
- 14 章【肥後藩】幕末京都における薩摩藩批判勢力の中心的存在 今村直樹
- 15 章【薩摩藩】島津宗家(久光)の動向からみる真の幕末史 町田明広
第3部 東北諸藩編
- 16 章【仙台藩】「奥羽の大藩」はなにを考えていたのか 栗原伸一郎
- 17 章【米沢藩】維新後にも現れた探索周旋活動の成果 友田昌宏
- 18 章【庄内藩】幕府への失望を抱えた「譜代第一」の命運 今野 章
- 19 章【秋田藩】戊辰戦争の「勝利」が引き起こした禍根 畑中康博
終章【版籍奉還】藩はどのようにしてなくなったのか 青山忠正
コラム 幕末維新史を知るためのキーワード 篠崎佑太
なぜ「藩」の呼び名は曖昧なのか
大名の家格はどのように決められていたのか
華族となった大名はどんな役割を担ったのか